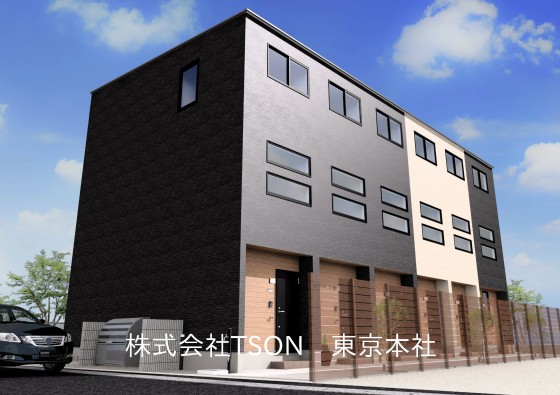2024年3月24日
借地権とは?権利の種類やメリット・デメリットを解説
借地権は「建物の所有を目的に土地を使用する権利」のことです。所有権に比べて低額で取引されます。借地権の物件は初期費用を抑えて不動産投資を行えます。一方継続的に地代が掛かるなどのデメリットがあります。
この記事で分かること
- 借地権は建物の所有を目的に土地を借りる権利
- 現法制下での借地権は「定期借地権」が一般的
- 借地権は初期投資が抑えられる反面、ランニングコストや出口戦略でデメリットがある
借地権は建物の所有を目的に土地を使用する権利
借地権とは1992年施行の借地借家法で定められた「土地を利用する権利」です。「建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権」と規定されています。
このうち地上権は、土地の利用方法に関しても、権利自体を譲渡することも基本的に貸主の承諾が不要な「物権」の一種とされ、賃借権よりも強い権利です。
現実的には特定の事情を除き地上権を設定しているケースは多くありません。そのため、この章ではより一般的な「土地賃借権」を前提に説明します。
借地権が成立する要件
借地権が成立する要件は、借地借家法の規定に該当する場合に成立します。具体的には「建物の所有を目的としていること」「有償であること」「有効な土地の賃貸借契約を締結していること」の3点です。
つまり、駐車場として更地のまま利用する場合や、無償で借りる場合などは借地借家法が適用されないため、借地権は成立しません。
これらの場合には民法による規定が適用されます。もしくは農地の賃貸借で農地法が適用されるように、別の法律による規制を受けます。
なお、借地権が設定された土地は「底地」と呼ばれます。
借地借家法と旧借地法との違い
借地権の理解を深めるためには、現行の借地借家法と旧借地法の違いを知っておく必要があります。
借地借家法は借主の保護を目的とした民法の特別法という位置づけです。それまでの借地法や借家法、建物保護法を統合して1992年8月に施行されました。
旧法も「借主の保護」を目的としている点では同様です。しかし、借主を保護しすぎる傾向がみられ、貸主に不利益が生じる側面がありました。旧法に規定された借地権では、期間の定めはあるものの貸主が更新を拒むことが困難だったため、「一度土地を貸したら返ってこない」という弊害を生んでいたのです。
これが地主に借地権の設定を躊躇させる要因ともなっていました。そのため、存続期間や更新の定めなどを一新し、明確化したのが新しい借地借家法です。
借地権の種類
借地借家法に基づく借地権には、更新の定めの違いによって大きく普通借地権と定期借地権とに分けられます。
いずれも契約の存続期間は定めるものの、普通借地権は継続的な更新が可能です。一方で、定期借地権には原則として更新はなく、契約終了後は返還しなければなりません。
それぞれの具体的な内容をみていきましょう。
借地借家法に基づく普通借地権
普通借地権とは、現行の借地借家法によって規定された「更新のある借地権」のことを指します。契約満了の際に借主が更新を希望すれば、地主側に更新を拒否する正当事由がない限り契約が更新される仕組みです。
借地権の存続期間は合意によって定めることができます。ただし30年以上が原則で、期間を定めなかった場合や30年未満の期間を定めた場合は30年とみなされます。なお更新は1回目は20年、2回目以降は10年が最低の期間です。
契約期間が満了した時点で借地人の建物が残存している場合は、地主に対してその建物の買い取りを請求できる点も特徴です。
定期借地権
期間の満了に伴って、契約の更新をしない旨の定めを付した借地権が定期借地権です。
普通借地権に比べて借主の権利が制限されます。そのため存続期間の定めや契約方法に関して普通借地権とは異なる規定が設けられています。
定期借地権は借地借家法の施行によって制度化されたものです。これによって「借地権を設定した土地は、半永久的に返還されない」という旧法の弊害を解消しました。
なお、定期借地権は残存期間や契約内容によって以下の3つの形式に分けられます。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
一般定期借地権
契約の存続期間を50年以上とすることで、更新を認めない仕組みの借地権です。一般定期借地権では、借地人建物買取請求権が認められません。また契約期間満了後に建物が残存していたとしても、借主は更地にして返還しなければなりません。
なお、一般定期借地権の契約は、書面での契約が義務付けられています。
事業用定期借地権
借地上に建築する建物が事業用である場合に限って設定できる定期借地権です。店舗や倉庫などの用途の建築物に適用できます。一部でも居住用部分がある場合には用いることができません。
事業用定期借地権では、当初契約の存続期間を10年以上50年未満として定めます。なお「30年以上50年未満」の場合と「10年以上30年未満」の場合では扱いが多少異なります。
「30年以上50年未満」と定めた場合には、契約の更新も建物買取請求権も認めない「特約を定めることがができる」とする一方で、「10年以上30年未満」の場合は特約がなくともこれらの規定が適用されません。
また、事業用定期借地権の契約は一般の書面では認められません。こちらは公正証書によらなければならないとされています。
建物譲渡特約付借地権
契約期間の満了後に借地人の建物を地主が買い取る旨の特約を付した定期借地権です。
契約の存続期間は30年以上とされています。期間は更新はできないものの、建物の残存価値に相当する対価を得ることで借地権者が保護される仕組みです。
このため他の定期借地権のような「書面による契約」などの制限が課されていません。
旧借地法に基づく借地権
旧借地法では、現行法に定める「定期借地権」という概念が存在しませんでした。どちらかと言えば旧法借地権は現行の普通借地権に近い性質のものでした。つまり、借地権者が更新の要求をした場合には、正当事由がなければ地主が拒むことができない仕組みです。
現行法の普通借地権との大きな違いは、コンクリート造などの堅固な建物と、木造などの非堅固な建物で存続期間が異なっていることです。堅固な建物は60年、更新後の期間は30年と規定されていました。また非堅固な建物は存続期間30年、更新後は20年と規定されていました。
さらに、契約を更新した後に建物が滅失した場合、現行の普通借地権は借地権契約を解除できるとしています。しかし旧法では原則として解約できませんでした。
🆕新着物件情報🏘️
借地権のメリット・デメリット

不動産投資を行う上では、いわゆる「割安な物件」の購入がアドバンテージになります。その観点で不動産を探していると、土地の権利が「借地権」とされた物件に出会うこともあるでしょう。
借地権の物件は所有権に比べて低価格であることが多いです。そのため同じ賃料でも高利回りが期待できるメリットがあります。一方で、生じるデメリットがあることも忘れてはなりません。
でも借地権のメリットとデメリットについてもしっかりと認識しておきましょう。
借地権のメリット
土地権利が「所有権」である物件に比べて割安で取得できる可能性が高いことがメリットです。
まずはメリットをみていきましょう。
初期費用を抑えられる
不動産投資において、最も大きな費用負担が生じる場面が「物件の購入」です。借地権は所有権に比べて低額で入手することができます。そのため物件購入時の初期費用を大幅に抑えられるのがメリットです。
借地権付きの物件を購入することで所有権を得るのは建物だけです。土地の所有者は地主のままとなります。このため地主に対して地代を払う義務が生じます。とは言え、土地の所有権を取得する場合と比較して割安で購入することができます。
土地分の固定資産税などの負担がない
不動産を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税などの税の負担が生じます。ただしこれは所有者に課される税金であるため、借地人は負担する必要がありません。また、不動産を取得した際に課される不動産取得税の対象も「所有権の取得」とされています。そのため借地では土地の税金を負担する必要がないのです。
ただしこれらの負担が生じないのは、あくまでも土地に関する税に限られます。土地の権利が借地権であっても、建物は借地人が所有者となるため、これらの税を負担しなければなりません。
旧法借地権は永続的に土地を借りられる
その物件の借地権が定期借地権でなければ、借り手側の意向によって永続的に借り続けることが可能です。
契約更新の際に建物が存続していることなどの条件はあるものの、賃借人からの更新の請求に対して地主にこれを拒絶する正当事由がない限り、契約が更新される仕組みだからです。
新法制下で設定された借地権であれば、定期借地であるものがほとんどといえます。しかし旧法に基づいて設定された旧法借地権は現在も数多く存続しています。
新たな法律が施行されても、借地権が自動的に新制度に移行するわけではありません。地主と借地人が双方合意のもとで新たに契約を結び直さなければ、旧法の借地権のままで存続する仕組みとなっているのです。
つまり、その物件が旧法で設定された借地権であれば、半永久的に土地を利用できることになります。
借地権のデメリット
割安で入手できるからには、相応のデメリットが生じることも否定できません。
デメリットもしっかりと認識した上で検討することが大切です。
地代の負担が必要
借地権は「有償で借りる契約」に基づいて成立する権利です。そのため、土地を借りている限りは地代を負担しなければなりません。購入時の初期費用が抑えられる反面、ランニングコストが高くなるのです。
不動産投資で利回りを検討する際には、この費用負担を考慮しなければなりません。
投資期間が長期化するにしたがって、「初期投資が抑えられる」というメリットが薄らぐ可能性があります。
建物の売却や増改築に制限がある
賃借した土地に借主が建物を建てた場合は、これを地主の許可なく売却することができません。地上権であれば自由に売却できますが、現実的には賃借権である場合がほとんどです。
また増改築の際にも独断で行うことができず、地主の承諾が必要とされます。これらの制約が加わることが借地権のデメリットです。
さらに、このような制約があることから、物件の流動性が低くなる弊害も生じます。
不動産投資では、主たる目的である「賃料による収益」の効率を重視しなければなりません。一方で、最終的に物件を売却するなどの「出口戦略」も疎かにしてはなりません。
建物の売却や増改築に関する制限は、投資戦略に関する制限であるともいえるのです。
融資のハードルが高い
物件の取得に際して金融機関からの融資を充てるケースは少なくないでしょう。しかし借地権の物件では融資のハードルが極端に高くなる傾向がみられます。このように資金調達が難しくなることも、借地権のデメリットの1つです。
不動産の購入で融資を受ける場合には、その物件を担保にして抵当権を設定するのが一般的です。しかし借地権は「土地を借りる権利」に過ぎませんから、抵当権を設定する可否判断は地主でなければできません。
確かに建物は借地人の所有ですから抵当権を設定することも可能ですが、そもそも土地の権利が付随しない建物に抵当権を設定するのは合理的とはいえません。
このような理由から、借地権の物件では金融機関から融資を受けることが難しいとされているのです。
借地権の第三者への対抗要件
不動産の所有権は「登記がなければ第三者に対抗できない」とされていますが、借地権を第三者に主張するにはどのような手続きが必要でしょうか?
借地借家法第10条には、次のように定められています。
| 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 |
つまり、借地権の第三者への対抗要件は「借地権の登記」もしくは「借地上の建物の登記」です。
また同法第10条の2で、建物が滅失した場合の対抗要件についても明らかにしています。
| 2.前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。 |
この規定では、滅失から2年間は建物の特定に必要な事項などを掲示すれば、対抗要件を備えるとされているのです。
借地権の特徴を知り投資戦略に生かそう
不動産投資では、初期投資を抑えるという点で借地権が有効に作用するケースも考えられます。しかし一方で、地代の負担によるランニングコストの増加や、借地権ならではの制約によって自由な賃貸経営が制限されることでデメリットが生じることも否めません。
特に出口戦略では、借地権であることがマイナスに作用する可能性が低くはないでしょう。
このような特徴を知り、メリットとデメリットをしっかりと把握して投資戦略に生かすことが大切です。
関連記事
-
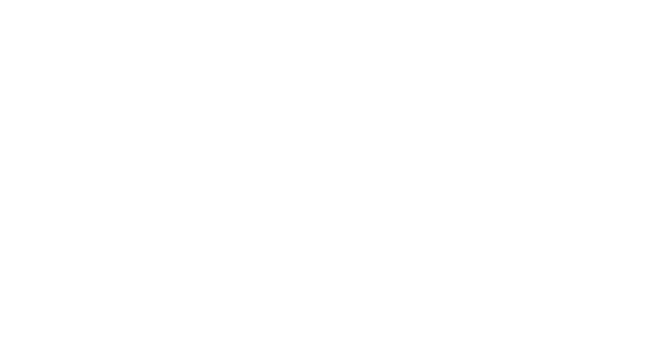 困った入居希望者の特徴9選!断る方法と注意点2024-03-28⻑い間空室になっている物件に申し込みが入ると、入居者がどんな人なのかを確認せずつ......
困った入居希望者の特徴9選!断る方法と注意点2024-03-28⻑い間空室になっている物件に申し込みが入ると、入居者がどんな人なのかを確認せずつ...... -
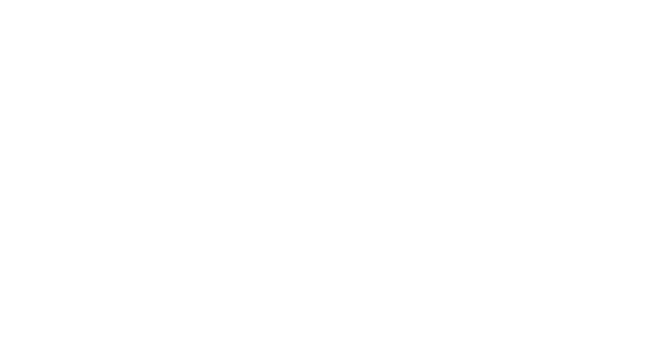 不動産にかかる税金は?知らないと怖い取得にかかる税金2024-03-26不動産には取得・保有・売却などさまざまな場面で税金が課されます。そのため、不動産......
不動産にかかる税金は?知らないと怖い取得にかかる税金2024-03-26不動産には取得・保有・売却などさまざまな場面で税金が課されます。そのため、不動産...... -
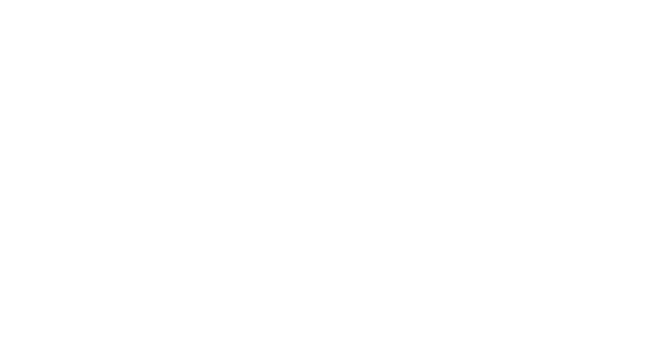 客付け方法10選!注意するポイントも解説【賃貸】2024-03-27不動産投資を安定させるためには、いかに効率的に客付けを行って空室期間を短縮できる......
客付け方法10選!注意するポイントも解説【賃貸】2024-03-27不動産投資を安定させるためには、いかに効率的に客付けを行って空室期間を短縮できる...... -
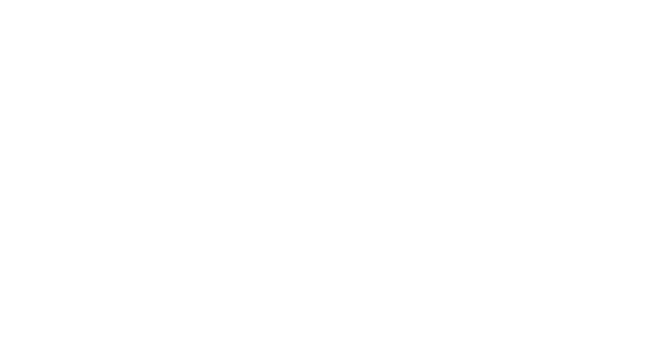 賃貸物件の巡回で重要なチェック箇所8選!2024-03-28不動産投資は「不労所得」と思われがちです。しかし物件価値を保つためには定期的な物......
賃貸物件の巡回で重要なチェック箇所8選!2024-03-28不動産投資は「不労所得」と思われがちです。しかし物件価値を保つためには定期的な物...... -
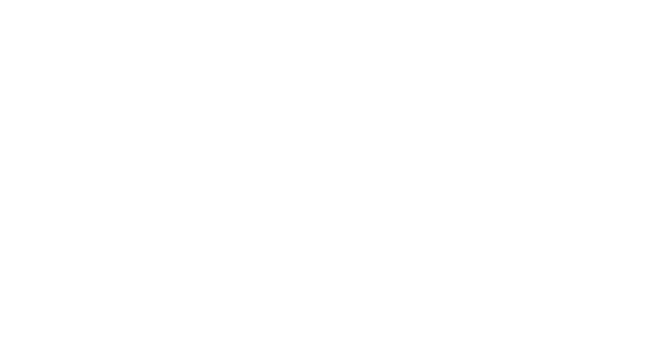 宅建士と宅建取引業者の違いとは?資格・免許の取得方法も解説2025-04-07宅建士は重要事項説明などを担う資格者、宅地建物取引業者は免許を持つ事業者です。2......
宅建士と宅建取引業者の違いとは?資格・免許の取得方法も解説2025-04-07宅建士は重要事項説明などを担う資格者、宅地建物取引業者は免許を持つ事業者です。2...... -
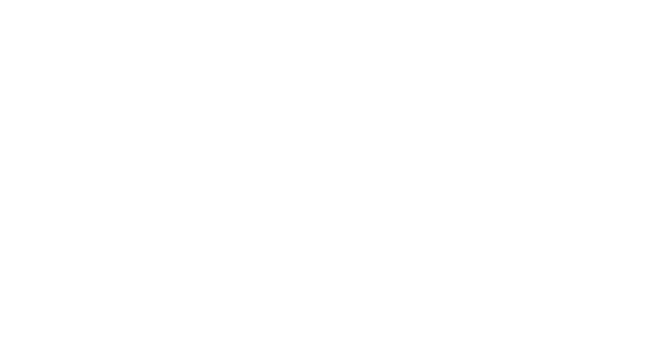 借地権物件◇不動産投資の基本戦略2024-03-26不動産投資で「借地権」が設定されている物件に当たることがあります。借地権は、特に......
借地権物件◇不動産投資の基本戦略2024-03-26不動産投資で「借地権」が設定されている物件に当たることがあります。借地権は、特に......