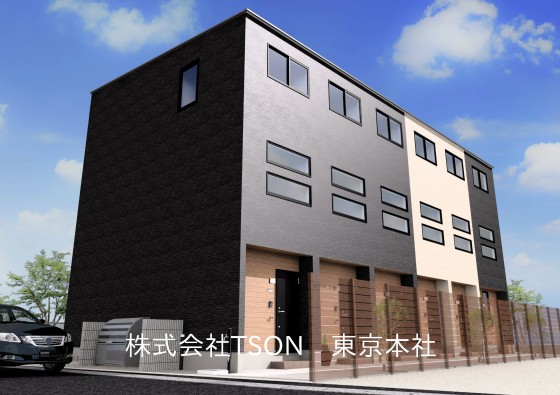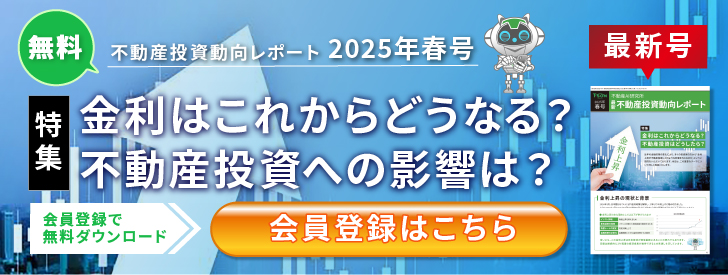2024年3月24日
不動産投資「なぜ利益が発生するのか?」
不動産投資をしようと思っている・実際にしている方はかなり多くいらっしゃいます。一方で、「なぜ利益が発生するのか?」について理論的に説明ができる人というのは意外に多くありません。このコラムでは、「なぜ 不動産投資で利益が生まれるのか」を理論的に説明します。
所有とレンタルの差額
あなたが5千万円持っていたとします。それで一軒家を買います。 その一軒家を月30万円で貸します。年間の売上は360万円です。 維持管理や税金にだいたい、毎年賃料の10%程度がかかります。したがって、粗利は324万円です。これを15年ちょっと続けると5,000万円が回収できます。そしてそれ以降は全部利益となります(実際には毎年所得税も発生します)。これが基本です。
5千万円の使い道は物件購入だけに限りません。例えば250万円の車を20台買って、レンタカー屋をすることも出来ます。仮に1台の車を1日1万円、回転率が50%とすると、年間の売上は1台あたり182万円、20台で3,640万円になります。ここから家賃や人件費、メンテンナンスフィーなどが売上の約半分程度かかるとすると、粗利は1,820万円。約2年半で投資金額をすべて回収できる計算になります。
不動産投資の利益率は低い?
不動産投資の利益率は他のレンタル事業に比べ低く見えるかもしれません。しかし、他のレンタル事業は、「単価」✕「回転率」ー(「固定費」+「流動費」)という、少なくとも4つのパラメーターがあります。そして各パラメーターが景気などに応じて複雑に変動します。そのため、各パラメーターがどのぐらいになるのかを知らないと、利益を出すことは難しいです。
それに対して、不動産投資の場合はパラメーターの変動が少ないのが特徴です。取るリスクも小さいので、他のレンタル事業よりも利回りが低くなっているのです。
レバレッジ
初期費用の回収に15年や20年かかり、そこからやっと利益が生まれてくるというのは、ずいぶん息の長い話です。 その間には、建物の劣化や入退去、自然災害など様々なリスクにさらされます。 それらのリスクを考えるとあまり魅力的なビジネスに見えません。
そこで、多くの場合、不動産投資では「レバレッジ」を活用します。
先程の例で、初期費用5千万円のうち、自分は1割の500万円を負担し、残りの4,500万円を金融機関から借りたとします。仮に金利1.5%で30年借りると、1年あたりの返済金額は約283万円です。粗利が324万円なので、41万円が手残りとなります(実際には所得税も引かれます)。そうすると、初期投資の回収は12年程度に短縮されます。
このように、借り入れを利用することで自分の手持ち資金の何倍もの資産を取得し、利益率を上げることを「レバレッジ」といいます。不動産投資ではレバレッジを活用して初期投資の回収を短くすることが目的の一つです。この場合、不動産を担保に借り入れるリスクを取ることが、利益の源泉となっています。
キャピタルゲイン
不動産の投資法としてキャピタルゲインを取りに行くという方法があります。これはここ数年特に都心部でマンション投資と言う形で多くの人が実践しています。
5千万円を10年間定期預金に入れたところで、5,050万円程度にしかなりません。(金利0.01%の場合)
それに対して、2013年ごろに5,000万円で購入できた2LDKの都内のマンションは、現在、8,000万円を超える価格で販売されています。これは物件の価格が上がったのではなく、インフレがあったためです。
もちろん、インフレではすべてのものの値段が上がります。それ以外の商品の価格も上がっているため「儲け」とは言い難いものがあります。例えば5,000万円で買ったマンションを9,000万円で売ったとします。そして売却益に対する税金を払った後の手残りの8,000万円で新たに2LDKの物件を買うとします。そのためには、5,000万円ではなく9,000万円が必要になるということです。売ったマンションよりも築年数が10年新しいものを買おうとした場合、さらに多くの金額が必要になります。
しかし、少なくとも定期預金に入れていたお金は50万円しか増えません。それに対しては利益が出ているという見方をすることができます。
インフレがなかったら?
一方で、もしインフレがなかったらどうなっていたでしょうか?もしインフレがなかったら、その物件そのものの価格で判断されることになります。マンションの場合、購入価格の土地/建物比率は建物に大きく偏っています。減価償却で大きく価値が下がるため、5,000万円の物件価値は3,500万円程度になっているでしょう。同じ期間にデフレが起こっていた場合、さらに金額が下がることになります。このように、マクロ経済動向や物件の劣化といったリスクを背負うことになります。
このキャピタルゲインは、「自分の手持ちの資金を何に投資するか?」という判断で、インフレに賭けてマンションを買うというリスクを取ったことに対するリターンと言えます。
🆕新着物件情報🏘️
開発リスク
また、最近行われている投資として「土地から新築」という方法があります。これは、土地を仕入れて、そこに新しい建物を建て、新築で出来上がった時点で売却する、というものです。
例えば、土地を5,000万円で買い、5,000万円を銀行から借り入れして1億円で物件を建てます。その物件を満室にして、賃料が800万円程度になったとします。それを利回り5%程度で売却すると、1億6千万円になります。
そこから借り入れ分を返済し、最初の持ち出し・税金・売却に関する諸経費を引いたとしても、3,500万円程度は手残りがあります。建築に約2年程度かかりますが、5,000万円を2年間で8,500万円にできます。そのため、急成長できる不動産投資方法として実践している人がいます。
「キャピタルゲイン」の場合、売主はマンションのデベロッパーとなりますが、そのマンションのデベロッパーが取っている利益を取りに行くという方法です。
しかし、これを実施するためには、建築するためのリスクや、業者の選定など、建築から法律、税金まで幅広いリスクがあり、かなり難易度の高い方法です。
最大のリスクとは
そして、最大のリスクが「建築会社が建築途中で倒産すること」です。これが発生すると、それまでに払った手付金などは一切返ってこないばかりか、中途半端に工事が進んでいるモノが残っており、これを仕上げてもらう新しい建築会社を探して、そこに続きの施工をしてもらうということになります。しかし、誰かが途中までやったものを引き受けて施工をしてもらうことは難しく、費用も大きく膨れがちです。場合によっては1億円でできたはずのものが2億円になり、1.6億で売れても全く利益が出ないどころか大きな赤字となる可能性があります。
この場合、「建築期間中の2年間の資金リスク」をひたすら背負うことになります。ハイリターンの裏には、ハイリスクがあるのです。
このように様々な利益の源泉があることをご紹介しました。
これ以外にも「民泊で利回りを更に上げる」「駐車場やコインランドリーで儲ける」といった事業収益を取りに行く方法もあります。
いずれにしても、「なぜ儲かるのか」を常に意識して、どの程度儲かればいいのか、何に投資して、何に投資しないかを意思決定していくことが大切です。
関連記事
-
 未払い⼊居者への正しい対処法とは?2024-03-28未払い入居者への対処は、大家業を営むうえで頭を抱える問題の1つです。すぐに追い出......
未払い⼊居者への正しい対処法とは?2024-03-28未払い入居者への対処は、大家業を営むうえで頭を抱える問題の1つです。すぐに追い出...... -
 連帯保証とは?連帯債務・ペアローンとの違い2024-03-27不動産投資を行う際、連帯保証や連帯債務という言葉を聞いたことがあると思います。こ......
連帯保証とは?連帯債務・ペアローンとの違い2024-03-27不動産投資を行う際、連帯保証や連帯債務という言葉を聞いたことがあると思います。こ...... -
 多法人スキームとは?概要とメリット・デメリット2024-03-28多法人スキームという言葉をご存じでしょうか。あまり聞き慣れないワード......
多法人スキームとは?概要とメリット・デメリット2024-03-28多法人スキームという言葉をご存じでしょうか。あまり聞き慣れないワード...... -
 マイソクとは?差別化するコツと5つの注意点2024-03-27入居付けをスムーズに行うためには、マイソクの内容を充実させるのがポイントです。さ......
マイソクとは?差別化するコツと5つの注意点2024-03-27入居付けをスムーズに行うためには、マイソクの内容を充実させるのがポイントです。さ...... -
 不動産セミナーの選び方!種類や参加前の準備などを解説2024-03-24不動産投資において、セミナーでの「学び」は投資を成功させるためには欠かせません。......
不動産セミナーの選び方!種類や参加前の準備などを解説2024-03-24不動産投資において、セミナーでの「学び」は投資を成功させるためには欠かせません。...... -
 所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他......
所有権とは?民法上の意味や動産・不動産の違いを解説2024-03-24所有権は、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利です。これは物を直接的・排他......