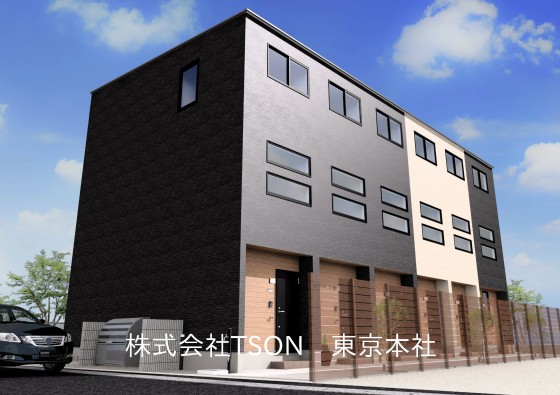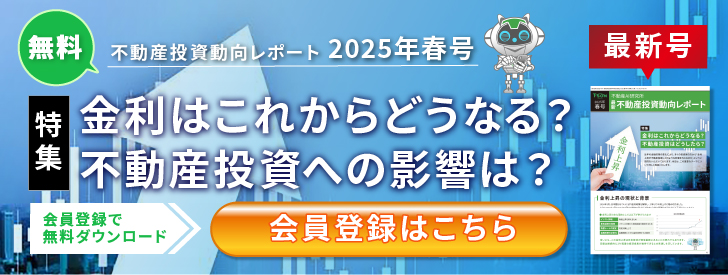2024年3月1日
競売
競売(けいばい)とは、住宅ローンの借り手である債務者が借り入れを返済しなかった時に、貸し手である債権者が担保に入れている不動産を裁判所の管理のもとで売却する手続きのことです。物件の情報は一般に広く開示されます。すべての人が同じ条件のもと入札を行い、最も高い値段をつけた人に落札されます。競売物件は事前に開示される情報が限定的であり、建物の中に入ることもできません。そのため、買い取りに伴うリスクを踏まえ、一般の売買価格よりも安く取引されます。
不動産投資や住宅ローンの返済が絡む場面でよく耳にする「競売」。テレビやニュースなどで競売物件の話題が取り上げられることも少なくありません。
しかし、実際にどのような仕組みで進行し、なぜ競売に至るのか?そして競売に掛けられた不動産がどう扱われるのか?といった点は詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
競売は、債権者が債務者から貸し倒れを防ぐ手段として、裁判所の手続きを通じて不動産を強制的に売却する仕組みです。そこには特有のルールやリスク、メリット・デメリットが存在します。本記事では、競売の基本的な仕組みから流れ、よくある質問までを包括的に解説します。
競売とは?基本的な仕組み
まず、競売とは何かを簡単に整理しましょう。競売とは、借金の返済が滞ってしまった債務者の所有する不動産を裁判所の手続きによって強制的に売却し、その売却代金から未払いの債務を回収する手段を指します。競売物件は、ローン返済が滞った自宅や投資用不動産など多岐にわたります。債権者は抵当権を設定し、返済が見込めないと判断した段階で裁判所に申し立てます。
競売物件は一般市場と比較すると割安な価格で落札されることが多いと言われています。主な理由は以下の通りです。
- 現況調査が十分にできないケースがある
- 占有者(元所有者や賃借人など)が退去しないリスクがある
- 瑕疵担保責任(売主が物件の欠陥を保証する責任)が免責される
これらを考慮して買手は入札金額を低めに設定しがちであり、市場価格より安く落札される傾向が生じます。そのため、債務者が十分な売却益を得られず、残債が残る可能性も否定できません。一方で、投資家にとっては「安く買えるチャンス」があるという魅力的な面もあります。
競売物件はインターネット上で閲覧することができます。
競売が行われる理由と背景
競売が行われる大きな理由の一つは、住宅ローンなどの返済が滞ることです。不動産を担保に融資を行う場合、金融機関は抵当権を設定しています。これにより、万が一の際には担保を処分して貸付金を回収できるようにしています。借主が何らかの事情で返済できなくなったとき、金融機関は債務不履行(デフォルト)として借主に対し競売手続きを踏むよう求めます。
競売申立はあくまで「最終手段」です。そのため、多くの場合はリスケジュール(返済条件変更)や任意売却などの代替手段を提案されます。しかし、これらの交渉がうまくいかない場合や、債務者が失踪・連絡不能などの事態に陥った場合には競売によって処分が進むのが現実です。
また、近年ではコロナ禍や景気変動、金利上昇リスクなどの要因によって、ローン返済の負担が重くなっています。今後は競売が増加するということもあり得るでしょう。不動産投資の場合、家賃収入が想定より下回ったり、空室が増えたりしたことでキャッシュフローが悪化し、ローン返済が困難になるケースも散見されます。競売は金融機関にとっても大きなコストと時間がかかります。債務者との話し合いを重ねても解決が見込めないときにやむを得ず申し立てる、という流れが多いです。
競売の流れと手続き
競売の大まかな流れとしては、以下のような手順をたどります。
1.競売申立の準備
金融機関(または債権者)が債務者に返済を再三求めても応じない、あるいは連絡が取れない場合、最終的に裁判所へ競売の申し立てを行います。ここでは、抵当権の存在と債務の不履行が確認できる証拠書類が準備されます。
2.開始決定と調査
裁判所は競売申立を受理すると、執行官や不動産鑑定士が物件の調査を行います。これは「現況調査報告書」と「評価書」を作成するためのステップです。物件の状況や市場価格を確認し、落札の目安となる売却基準価格を算定します。
3.売却公告と入札期間
調査が終了すると、裁判所は物件情報や売却基準価格を公示します。そして入札参加者(一般投資家など)を募集します。入札期間や開札日が指定され、物件資料(公告や評価書)を閲覧して検討した人々が、その間に入札価格を決定し、入札書を裁判所へ提出するのです。
4.開札・落札と代金納付
開札は裁判所内で行われます。入札者が提示した金額を開封・確認し、最高額の入札者が落札者となります。落札者は指定された期日までに競落代金を支払う義務を負います。これが完了すると不動産の所有権が落札者に移ることになります。
5.配当手続き
売却代金は競売にかかった費用などを差し引き、抵当権者や差押債権者など利害関係者に優先順位に従って配当されます。残った金額があれば、元の所有者(債務者)に戻ります。しかし、売却代金がローン残債などの債務を全額カバーできなかった場合、競売後も借金が残ってしまう可能性があります。
競売にかけられた物件を第三者が落札する場合、占有者の立ち退き交渉などの問題が残る場合があります。買い手にとってもリスクは小さくありません。とはいえ、落札価格が市場相場より低めに設定されやすいため、投資家にとってはチャンスとなることもあるのです。
🆕新着物件情報🏘️
競売の注意点とリスク管理
競売は、売る側にとっても買う側にとっても特有の注意点が存在します。
売られる側(債務者)のリスク
まず、売られる側(債務者)にとっては「不動産が強制的に処分されるうえ、市場価格より低く売られることが多い」ため、結果的に多額の残債を抱えるリスクがあります。一度手続きが開始すると、任意売却などの処分方法に切り替えるのが困難になります。そのため競売申し立てが行われる前に金融機関との話し合いを重ね、別の解決策を模索することが大切です。
買う側(入札者)のリスク
一方、買う側(入札者)にとっては、物件の内部を十分に確認できない点がリスクです。また瑕疵担保責任が免除されているなどのリスクもあります。さらに、物件に居住者やテナントがいる場合には、落札後の立ち退き交渉が必要になるケースもあります。こうした問題があるため、競売物件を購入する場合は「安く手に入る」だけに飛びつくのではなく、事前調査やリスク対策を十分に行う必要があるのです。
投資家として競売物件を狙うのであれば、まずは「売却基準価格」や「評価書」だけでなく、周辺相場や物件の建築年代、構造、修繕履歴、隣接地との境界状況などをできるだけ把握し、落札後のリスク管理を徹底しましょう。物件情報が限られるため、入札に際しては保守的な評価を行います。想定外の出費が出たとしても致命傷にならないような資金計画を組むことが肝心です。
また、売却しても売却代金が借金を全て返しきれないケースは珍しくありません。この場合、債務者は残債務を引き続き返済しなければなりません。中には自己破産や個人再生など法的手段の利用を検討する場面もあるでしょう。したがって、競売はあくまでも「債権者が不動産を処分して貸金を回収する方法」であり、決して万能な解決策ではないという点を理解しておく必要があります。
よくある質問
競売と任意売却の違いはなんですか?
競売は裁判所の手続きを経て強制的に売却する方法です。市場価格よりも安くなる可能性が高い一方、任意売却は債務者と債権者の合意のもと、不動産会社などを通じて市場で売却を行う方法です。任意売却のほうが高値で売れる可能性が高く、残債の減少が見込みやすい特徴がありますが、債権者と条件交渉が難航する場合もあります。
競売物件は内見できないと聞きますが、本当ですか?
一般的には、競売物件の室内を事前に確認することは難しいです。裁判所の資料や現況調査報告書から判断するしかないケースが多く、物件内部の状況やリフォームの必要性などを正確に把握しづらいのが実態です。ただし、最近では占有者と協議し、内見可能な場合も一部にはあります。
競売で落札すれば瑕疵担保責任は追及できますか?
競売不動産は「現状有姿」での売買が原則であり、瑕疵担保責任は一切免除されます。後から重大な欠陥が見つかっても、落札者が費用を負担して修繕しなければならないことが多いです。そのため、価格設定や事前調査を慎重に行わないと、想定外のリスクを被る可能性があります。
競売開始後でも借金を全額返済すれば競売は止められますか?
基本的には、競売手続き中でも借金を一括返済すれば競売は取り下げられます。しかし、実際にはそれだけの資金を調達できるかが大きな問題となるでしょう。金融機関に任意売却や条件変更を相談するタイミングも考慮し、早め早めの対策が肝要です。
競売で売却されたら借金はすべてなくなりますか?
競売で得た売却代金が債務を全てカバーできれば完済になりますが、競売価格は市中相場より安くなる場合が多く、完済に至らないこともしばしばあります。売却代金では返済しきれない残債務は、引き続き債務者が返済義務を負うことになります。
競売は、不動産投資家にとっては魅力的な物件を安く手に入れる手段である一方、従来の売買方法とは異なる独自のリスクや手続きが存在します。また、債務者にとっては高い確率で不利な結果(低い売却価格、残債の残存など)を招くため、極力避けたい事態であることに変わりはありません。競売に至るまでには、リスケジュールや任意売却など、他の選択肢を検討する余地があるので、返済が苦しくなった段階で早期に金融機関や専門家へ相談するのが望ましいでしょう。競売自体を理解し、その長所と短所、双方の立場からのメリット・デメリットを把握しておくことで、不動産投資や資金調達のリスク管理をより賢明に行うことが可能になります。
関連記事
-
 資金計画2024-03-01資金計画とは、投資や事業などの資金の使い道や調達方法を計画すること。不動産投資に......
資金計画2024-03-01資金計画とは、投資や事業などの資金の使い道や調達方法を計画すること。不動産投資に...... -
 差押2024-03-01差押(さしおさえ)とは、住宅ローンや税金を滞納した時に、債権者がそのお金を回収す......
差押2024-03-01差押(さしおさえ)とは、住宅ローンや税金を滞納した時に、債権者がそのお金を回収す...... -
 物件選定2024-03-01物件選定(ぶっけんせんてい)とは、不動産投資をする際に、適切な物件を選ぶこと。立......
物件選定2024-03-01物件選定(ぶっけんせんてい)とは、不動産投資をする際に、適切な物件を選ぶこと。立...... -
 延長敷地2024-03-01延長敷地(えんちょうしきち)とは、路地状敷地のことで、敷地の一部が通路状になって......
延長敷地2024-03-01延長敷地(えんちょうしきち)とは、路地状敷地のことで、敷地の一部が通路状になって...... -
 レントロール2024-03-01レントロールとは、部屋ごとの家賃の一覧表のことです。賃貸物件を所有しているオーナ......
レントロール2024-03-01レントロールとは、部屋ごとの家賃の一覧表のことです。賃貸物件を所有しているオーナ...... -
 43条但し書き道路2024-03-0143条但し書き道路(よんじゅうさんじょうただしがきどうろ)とは、建築基準法第43......
43条但し書き道路2024-03-0143条但し書き道路(よんじゅうさんじょうただしがきどうろ)とは、建築基準法第43......