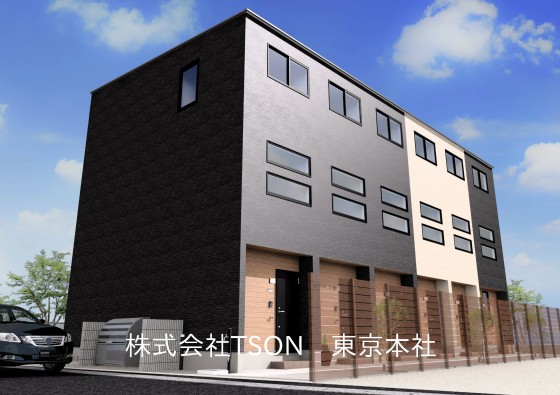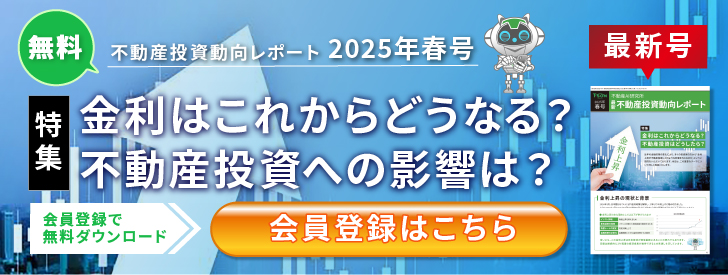2024年3月1日
変動金利
住宅ローンの場合、およそ半年ごとに金利が見直されます。 しかし金利が上がったからといって、すぐに返済返済額が上がるわけではありません。金利が上昇しても、毎月の返済額が急に上がるということがないよう、 「5年ルール」や「125%ルール」などの制度があります。
日本の変動金利住宅ローンは、2024年から2025年にかけて上昇傾向にあります。
金融政策の変化
2024年に日本銀行はマイナス金利政策を解除し、段階的な利上げを開始しました。
- 2024年3月:マイナス金利解除、政策金利を0~0.1%に設定
- 2024年7月:政策金利を0.25%に引き上げ
この政策変更により、変動金利の基準となる短期プライムレートが上昇しました。これは住宅ローン金利に影響を与えています。
そもそも変動金利とは?
変動金利とは、金融機関や市場の金利動向に応じて、一定の期間ごとに利率が見直される仕組みのことです。住宅ローンやカードローンなどで利用されることが多いです。例えば政策金利や市中金利の変動、また金融機関の調達金利などをもとに、定期的に金利が更新されます。
変動金利の特徴
金利の見直し時期
一般的に半年ごとや1年ごとなど、一定の期間ごとに金利の見直しが行われます。
返済額の変動タイミング
住宅ローンの場合、金利は半年ごとに見直されても、返済額が変わるタイミングは5年ごとなどと定められているケースがあります。これを「5年ルール」などと呼ぶこともあります。
元利均等返済方式が多い
変動金利型の住宅ローンでは、金利が上昇してもすぐに返済額が大幅に上がるということはありません。まずは返済額のうち“利息部分”が増え、元金の返済分が減るしくみになっています。ただし、その期間が長期に渡ると、後に返済額が大幅に上がる可能性もあります。
変動金利の動向
2024年10月以降、多くの金融機関で変動金利が0.4%台に上昇しました。具体的な変化として以下が挙げられます。
- 大手銀行5行は2024年10月から変動型住宅ローンの基準金利を0.15%程度引き上げ
- 一部の地方銀行でも、2024年10月から変動型住宅ローンの基準金利を0.15%引き上げ
2025年の見通し
2025年も変動金利の緩やかな上昇が予想されています。
- 日本銀行は2025年度後半に向けて、段階的に政策金利を1.0%まで引き上げる可能性を示唆
- 2025年末時点の政策金利は0.5%かそれ以上に達する可能性がある
ただし、経済情勢や物価動向によっては、利上げのペースが変わる可能性もあります。
🆕新着物件情報🏘️
借り手への影響
変動金利で住宅ローンを組んでいる人は、今後の金利上昇に備える必要があります。
- 既存の借り手は、2025年1月の返済分から新たな金利が適用される可能性がある
- 返済額の急激な増加は抑えられるものの、長期的には総支払い利息が増加する可能性がある
変動金利の上昇傾向を踏まえ、借り手は自身の返済計画を見直すことが大切です。また必要に応じて固定金利への借り換えなどを検討することが重要です。
よくある誤解・質問
1. 「金利が上がったらすぐに返済額が増える」
誤解
変動金利では金利が少しでも上昇したら、次の返済から即座に返済額が大きく跳ね上がると考えてしまう方がいます。
実際
変動金利型の住宅ローンなどでは、金利自体は半年に一度見直されます。ただし返済額が変動するタイミングは通常5年ごとやルールによって定められています。そのため、金利が上昇しても返済額がすぐに大幅に上がるとは限りません。しかし、一定期間が過ぎた段階で、返済額がまとめて引き上げられる可能性があります。
2. 「固定金利よりも常に安い」
誤解
「変動金利」は「固定金利」よりも常に金利が低く、おトクであると思い込んでしまう方もいます。
実際
変動金利は、あくまで金融市場の動きによって利率が決まります。そのため、上昇局面になれば固定金利より不利になる場合もあります。特に長期的な金利上昇が続く場合には、返済総額が想定以上に増えるリスクもあります。
3. 「市場金利が少しでも上がれば、返済困難になる」
誤解
金利が少し上昇しただけで返済が不可能になってしまうと考えるケース。
実際
金利上昇で月々の返済額は増加する可能性があります。とは言え一度に大きく跳ね上がるわけではありません。ただし、長期にわたる金利上昇や数%単位の大幅な利上げがあった場合は、返済計画に大きな影響を与える可能性があります。そのため、事前に金利上昇のリスクを踏まえた返済計画を立てることが重要です。
4. 「変動金利は将来の予測が難しく、手を出さないほうがいい」
質問・不安
将来の金利動向を読むのは難しいから、変動金利は危険なのでは?という懸念。
実際
確かに、将来の金利動向は正確には予測できません。一方で、固定金利よりも変動金利が低水準で推移すれば、結果的に利息の支払い総額が少なくなる可能性があります。
- 選択のポイント
- 長期的な金利上昇リスクをどこまで許容できるか
- 金利が上昇した場合に、家計収支をどこまで対応可能か
- 固定金利と変動金利をミックスする「ミックスローン」を検討するか
など、自身の収入や生活プラン・リスク許容度に合わせて検討することが大切です。
5. 「金利が下がれば返済額はすぐに下がる?」
誤解
金利が下落すればすぐに返済額が減ると考えてしまうケース。
実際
金利の下落自体は半年ごとに反映されるものの、返済額に反映されるタイミングは住宅ローンの商品特性(返済額見直しのルール)によって異なります。銀行によっては、月々の返済額よりも元金の減り方やボーナス返済の額に反映される形が優先されることもあります。
まとめ
- 変動金利は、市場の金利動向にあわせて利率が定期的に見直されるローン・預金の金利タイプです。
- 変動金利が低水準の時期には利息負担を抑えられますが、将来の金利上昇リスクを抱えることになります。
- 「半年ごとの金利見直し」と「5年ごとの返済額の見直し」など、商品によって具体的なルールが異なります。
- よくある誤解や不安には、返済額の変動のタイミングや、固定金利との比較などがありますが、正しい知識を持っていれば計画的に利用できます。
- 重要なのは、ご自身の生活設計や将来のリスクへの備えをしっかりと考慮して選択することです。
変動金利のメリット・デメリットを正しく理解し、固定金利やミックスローンなど他の選択肢とも比べながら、自分に合った金利タイプを選ぶようにしましょう。
関連記事
-
 賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが......
賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが...... -
 接道2024-03-01接道(せつどう)とは、土地が公道などに面している状態のこと。建物を建てるためには......
接道2024-03-01接道(せつどう)とは、土地が公道などに面している状態のこと。建物を建てるためには...... -
 借地権2024-03-01借地権(しゃくちけん)は、建物を建てるために地主から土地を借りる権利のことです。......
借地権2024-03-01借地権(しゃくちけん)は、建物を建てるために地主から土地を借りる権利のことです。...... -
 不動産投資信託(REIT)2024-03-01REITとは「Real Estate Investment Trust」の略で、......
不動産投資信託(REIT)2024-03-01REITとは「Real Estate Investment Trust」の略で、...... -
 オフプラン投資2024-03-01オフプラン投資とは、建物が完成する前に購入する投資スタイルのこと。海外不動産投資......
オフプラン投資2024-03-01オフプラン投資とは、建物が完成する前に購入する投資スタイルのこと。海外不動産投資...... -
 私道2024-03-01私道(しどう)とは、個人が所有する他の土地への通行権を確保するための道。私道に関......
私道2024-03-01私道(しどう)とは、個人が所有する他の土地への通行権を確保するための道。私道に関......