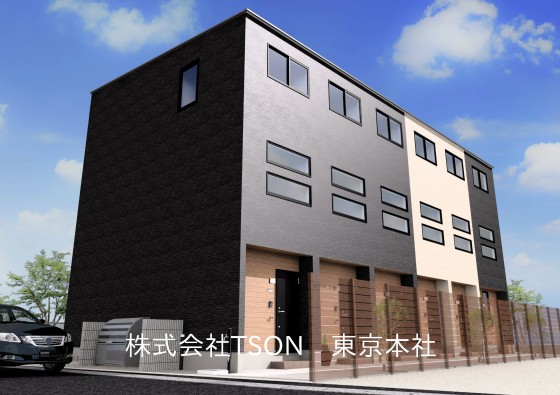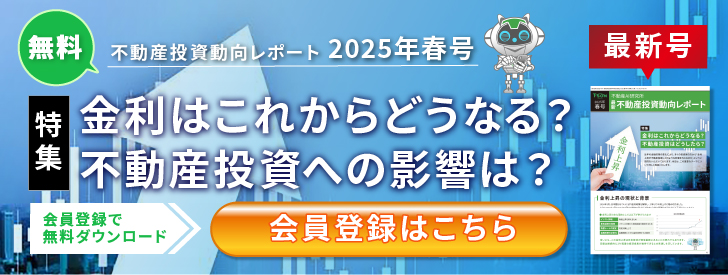2024年3月1日
固定資産税評価額
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)とは、固定資産税の課税基準となる土地や建物の評価額。
固定資産税評価額という言葉は、不動産を所有する際には避けて通れないものです。毎年送付される納税通知書にも記載されています。中には「家や土地の価値を市町村が算出しているもの」という漠然としたイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、算出方法や実際の税金への影響については、詳しく知られていません。
固定資産税評価額を正しく理解することでコスト計算が精密になります。これは長期的な資金計画にも役立ちます。本記事では、固定資産税評価額とは何か、算定方法と影響要因、確認する際の注意点やよくある質問などについて詳しく解説します。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、市町村(東京都23区の場合は都)が土地や家屋などの固定資産に対して、一定の基準に基づいて算出した評価額のことを指します。この評価額が固定資産税や都市計画税などの課税標準額として利用されます。結果として毎年支払う税金額に直結するため、所有者にとっては重要な数値といえます。
具体的には、次の式で固定資産税が計算されるケースが多いです。
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%が一般的)
この課税標準額が、一般には固定資産税評価額そのもの、あるいは特例が適用される場合には一部を減額した金額となります。つまり、固定資産税評価額が大きいほど、毎年支払う固定資産税が高くなります。一方で、この評価額はあくまでも税金計算上の評価であり、実際の売買価格(実勢価格)とは必ずしも一致しません。実勢価格の6~7割程度、あるいはそれ以下の水準になるケースが多いです。そのため「思っていたより安い評価だ」と感じる方もいるでしょう。とは言え、税額に直結する部分でもあるので侮れません。
評価額はどうやって算定される?
固定資産税評価額は、「固定資産評価基準」という国が示すルールに基づき、市町村の担当部局が個別の不動産について査定を行うことで決定します。
大まかな流れは以下のとおりです。
評価替えの周期
固定資産税の評価替えは原則3年に一度行われます。そのため、評価年度ごとの地価や建築費用、経年減価などの変動要因を踏まえ、基準年度となる年に各不動産の評価額が一斉に見直されるのです。
ただし家屋の新築・増改築や土地の区画整理などの事情があれば臨時で評価が行われる場合もあります。
土地の評価
土地については、路線価方式または倍率方式により算出されます。路線価方式を採用するエリアでは、道路に面した標準的な土地の価格(路線価)を基準として補正率をかけます。また形状や奥行き、方角などを考慮して個々の評価を行います。一方で倍率方式は、国税庁が公表する固定資産税評価倍率を用いて計算します。
なお、市街地や地価の高いエリアほど細かく路線価が定められていることが多いです。郊外や山林などでは倍率方式が用いられるケースが多く見られます。
家屋の評価
建物(家屋)の場合は建築したときの新築評点数をベースにします。ここに経年に応じた減価を反映して評価額を計算します。具体的には、構造や用途、床面積、設備グレードなどから点数を算出し、これに1点あたりの単価を掛けて新築時の価格を求めます。その後、年数が経過するごとに減価率を加味して評価額が下がっていく仕組みです。
なお、リフォームや増改築によって大幅な価値向上が見込まれる場合は、改築年に再評価が行われることがあります。
公示されない個別要因
例えば「眺望が良い」「駅から近い」「日当たりが悪い」などの個別事情は、基本的には評価に大きく反映されないことが多いです。一方で、土地の形状や接道状況、公共下水道の有無、建物の構造や耐火性能などの客観的要件は反映されやすいのが特徴です。
🆕新着物件情報🏘️
固定資産税評価額に影響する要因
固定資産税評価額は、下記のようなさまざまな要因によって変化します。
立地条件(エリア特性)
市街化区域かどうか、地価水準の変化、都市計画の進捗状況などが影響します。地価が上昇しているエリアでは評価替えのタイミングで評価額が上がりやすくなります。
土地や建物の形状
土地であれば間口が狭いか広いか、旗竿地かどうか、傾斜があるかなど。建物であれば構造、階数、延床面積、築年数、設備などが考慮されます。
経年による価値の減少
建物は築年数による経年劣化が評価額に反映されやすいです。固定資産税評価額も年々徐々に下がっていくのが一般的です。ただし、減価率は建物の構造によって大きく異なります。
リフォームや増改築
住宅を増築したり、設備を大幅にグレードアップするリフォームを行った場合、評価額の見直しが行われる可能性があります。結果として固定資産税が上がることもあります。そのため増改築を行う際にはその点を考慮して予算を組みましょう。
公共事業やインフラ整備
都市計画道路や鉄道の新駅建設など、周辺環境が大きく変わるプロジェクトが進むと、地価が高騰し固定資産税評価額にも反映される場合があります。
確認方法と注意点
固定資産税評価額は毎年4~6月頃に届く「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に記載されています。また、固定資産税の課税明細書にも評価額が記載されています。まずはそちらを確認するとよいでしょう。
さらに、市町村役場の固定資産税課や資産税課に申請すれば、固定資産税評価額の詳細な内容や評価根拠を閲覧できるケースもあります。特に評価替えの年には、市町村が評価額の閲覧期間を設けていることが多いです。そのため疑問がある場合はその期間中に確認するのが望ましいでしょう。
注意点としては、評価額が課税のベースになるため、家を新築したり建て替えたりすると固定資産税が大幅に上がる可能性があることです。さらには、築古物件を購入してリノベーションを行った場合も、増改築に該当する場合は翌年の評価額が見直されることがあります。改築前後の税額シミュレーションを行い、長期的な資金計画に組み込むことが大切です。
また不動産投資の場合、固定資産税評価額は相続税や贈与税の算定時の財産評価、または不動産取得税の確認にも関係する場合があります。用途や状況によっては評価額の基準が異なることもあります。そのため「固定資産税評価額=相続税評価額」と単純にイコールとはなりません。とは言え、概ね目安として活用されることも多いです。
よくある質問
固定資産税評価額と実勢価格はどのように違うのですか?
固定資産税評価額は税金計算用に市町村が一律の基準に基づき算定する評価額です。一方、実勢価格は市場で実際に売買される際の価格を指します。固定資産税評価額は実勢価格の6~7割程度といわれることが多いです。ただしエリアや物件によって差があります。
評価替えの年に大幅な値上がりがあった場合、いきなり税金が増えるのでしょうか?
理論上はそうなる可能性があります。ただし、大幅な地価上昇が起きた場合は、市町村が段階的に税額負担を調整する「負担調整措置」を講じることが多いです。一気に税額が高騰すると住民に大きな影響が出かねません。そのため段階的に税負担を増やしていく仕組みが用意されています。
築古の中古物件の場合、固定資産税評価額はどうなりますか?
一般的に、建物は築年数が経過するほど評価額が下がっていきます。木造住宅であれば築20~25年程度で建物評価額がほぼゼロに近づくことも多いです。ただし、土地の評価額は築年数で下がるわけではありません。築古でも土地が高額なエリアだと税額が高いままということもあります。
住宅をリフォームすると固定資産税評価額は上がるのでしょうか?
建築基準法に基づいた「増改築」に該当する規模の工事や、設備を大きく付加する工事を行うと、翌年度以降の固定資産税評価額が見直される可能性があります。小規模な内装リフォームなどでは評価に反映されない場合もありますが、大がかりな改築や設備追加がある場合は注意が必要です。
固定資産税評価額が納得できない場合、異議申し立てはできますか?
固定資産税評価額について疑問や不満がある場合は、まず市町村役場の資産税課などで評価の根拠資料を閲覧してみましょう。評価方法に誤りがあると感じる場合は、評価替えの年の「固定資産評価審査委員会」に審査請求を行うことができます。ただし、誤りではなく単なる価値観の違いに基づく主張だと棄却されるケースも少なくないため、手続きには注意が必要です。
固定資産税評価額は、年々発生する固定資産税額を決定づける重要な数値でありながら、実勢価格との乖離や計算基準の複雑さから理解が追いつかないケースが多々あります。しかし、不動産を所有・売買・投資する上では、必ず押さえておきたいポイントです。
評価替えのタイミングや増改築の有無に応じて金額が変動する仕組みを理解することで、将来の税負担を見通しやすくなり、資金計画や投資計画をより正確に立てることが可能になります。自分の所有している不動産の固定資産税評価額を定期的にチェックし、必要があれば市町村や専門家に相談するなど、適切なアクションを取ることが大切です。
関連記事
-
 不動産投資信託(REIT)2024-03-01REITとは「Real Estate Investment Trust」の略で、......
不動産投資信託(REIT)2024-03-01REITとは「Real Estate Investment Trust」の略で、...... -
 坪2024-03-01坪(つぼ)とは、不動産の面積の単位のこと。 1坪は約3.3平方メートル。坪は尺貫......
坪2024-03-01坪(つぼ)とは、不動産の面積の単位のこと。 1坪は約3.3平方メートル。坪は尺貫...... -
 一棟物2024-03-01一棟物(いっとうもの)とは、一つの建物全体を投資対象とすること。これに対して、分......
一棟物2024-03-01一棟物(いっとうもの)とは、一つの建物全体を投資対象とすること。これに対して、分...... -
 賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが......
賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが...... -
 不動産ブローカー2024-03-01不動産ブローカーとは、不動産取引において売買仲介を行う業者。市場価値の調査や契約......
不動産ブローカー2024-03-01不動産ブローカーとは、不動産取引において売買仲介を行う業者。市場価値の調査や契約...... -
 ROI2024-03-01不動産投資におけるROIとは? ROI(Return on Investment......
ROI2024-03-01不動産投資におけるROIとは? ROI(Return on Investment......